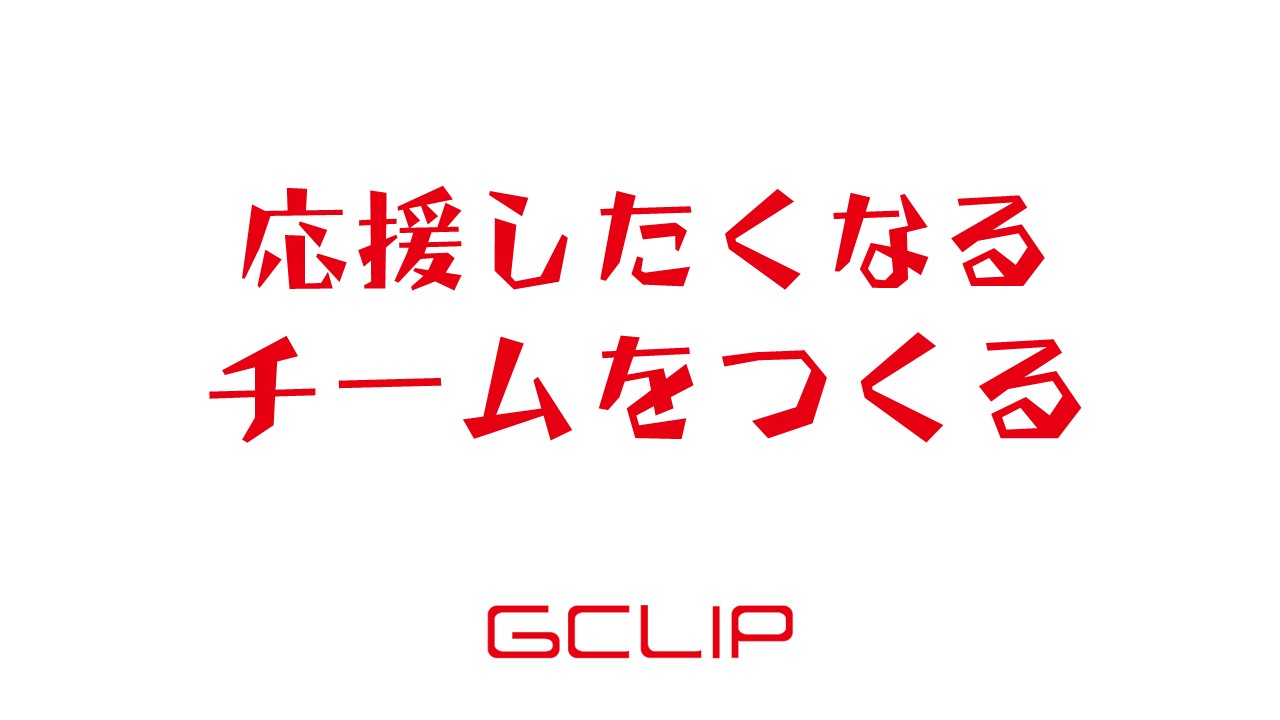==================
応援したくなるチーム (組織)をつくる
==================
<本文のポイント>
・1ON1による仙台育英高校のマネジメント
・理想の状態(日本一)から招かれる行いとは?
・理想の状態(日本一)から招かれる行いとは?
・評価基準を明確化してビジョンを描ける状態をつくる
・利便性を包み込み、独自性で一点突破しよう!
<本文>
8月17日(日)午前8:00第1試合。
第107回全国高校野球選手権の3回戦にコマを進めた
第107回全国高校野球選手権の3回戦にコマを進めた
宮城代表の仙台育英高校は、
ベスト8をかけて沖縄尚学(沖縄代表)と対戦し、
延長11回にわたる接戦のゲーム展開の末、
残念ながら3対5で敗退することとなりました。
仙台育英の須江航監督には
2年前のGCLIP10周年セミナーにご登壇いただき、
若者の指導における示唆に富んだ話をしていただいて以来、
仙台育英高校の試合は注目して観戦しています。
特に印象的なのが須江監督は選手との関係構築において、
1ON1による対話を重要視しているところです。
講演の中で、1対多数でいくら熱弁をふるっても、
それはなかなか相手に伝わらないし、忘れてしまう。
100人に伝えて伝わるのはその1割ぐらい。
その1割が理解するのは全体の10%くらい。
このように1対多数は伝わらないから、
須江監督は1対1で丁寧に伝えると話していました。
1対1の話し合いというのは、
相手との間に会話のキャッチボールがないと成立しません。
1対多数の場合は逆に
キャッチボールをしていては成立しにくくなります。
どちらの方が相手との信頼関係が構築できるかというと、
やはり1対1のキャッチボール型なのです。
仙台育英高校は2022年夏に甲子園で優勝し、
2023年には決勝で惜しくも敗れていますが、
2年連続甲子園で決勝戦を戦っています。
選手も入れ替わり、対戦相手も変わり、
あらゆるコンディションが変化する中で
再現性の高い勝ちを収めるマネジメントを実現しています。
その基本がこの1対1にあるのだと思います。
2023年8月29日号の本メルマガで弊社林は
仙台育英のマネジメントを次のように指摘しています。
——————————
実は監督として活躍されている方は
自分の現役時代はあまり活躍していなかったケースが意外に多いの
例えば青山学院大学駅伝部の原監督も
現役時代の成績は目立ったものはなかったと公言しています。
さて、こういった監督がなぜ成果を出すのかというと
「自然にできてしまう人」は「できない人」
「どうやってできるようになるのか」
ということが理由であるようです。
森林監督も、須江監督もだからこそ伝え方にこだわりを持ち、
選手に丁寧に伝えています。
そして、二人とも大切にしていると公言していることが
「対話」「傾聴力」です。
選手の話を聞き、選手自らが考え、行動できる雰囲気づくりを
徹底して作っているのです。
伝え方にこだわり、しっかりと対話をする。
これが二人の共通点であり、
強いチームを作る一つのポイントだと考えられます。
——————————
対話と傾聴力。
どうやってできるかを言語化する能力を生かすためには、
伝え方にこだわり、
しっかりと対話(=相手を受け入れて、自分を受け入れてもらう)
することが組織を強化していくための
自立的で自律的なチーム作りには欠かせないということです。
プレーヤーとマネージャーがこのような1対1の対話を繰り広げる
互いをよりよく理解することができるので信頼関係が構築されます
これを象徴するエピソードが甲子園優勝を果たした、
2022年夏の明秀日立(茨城)との3回戦にあります。
以下、須江監督の著書より引用。
——————————
2点を追う7回裏、右腕・猪俣駿太投手から、
一番の橋本航河がレフト前ヒットで出塁すると、
山田脩也がしぶとくレフト前に運び、無死一、二塁。
続く秋元響に、送りバントのサインを出すか、
あるいはミート力に長けたバッティングに託すか、
少し心配だったのが、秋元のバッティングの状態です。
初戦、そしてこの試合の3打席目まで見るかぎり、
ただ、猪俣投手の調子も決して万全には見えず、
送りバントでアウトをあげることが、
私は攻撃のタイムを取り、背番号13を着けた
キャプテンの佐藤悠斗を秋元のところに向かわせました。
「監督は腹を決めている。お前に打たせたい。
お前の力なら、出塁を取って、チャンスを広げられる。
それでいいと思うのなら、ベンチに向かって丸を作ってくれ。
もし、自分が不調で、バントで送ったほうが確実だと思うのなら、
そのまま打席に向かってくれ」
佐藤に授けた言葉です。
言葉を受けた秋元は、ベンチに向かって丸を描いてくれました。
秋元は初球、ストライクゾーンのストレートを見逃したあと、
変化球を見極めて、2ボール1ストライク。
ここからファウル、ボール、
インハイのストレートをしっかりと見逃して、
狙い通りにフォアボールを奪い取ってくれました。
その瞬間、秋元は、「ヨッシャ!」
この出塁がどれだけ大きなものか、よく理解したうえで、
見事に役割を果たしてくれたのです。
——————————
マネージャー(監督)が適切な判断をするために、
プレーヤー(選手の性格や特徴)をよく理解し、
迷う場面では最終的にプレーヤーの判断に委ねる。
信頼関係があって初めてできることです。
「日本一からの招待」をスローガンに掲げる
仙台育英高校は、日本一から招待されるチームになるべく
行動、発言、練習など行いを徹底しています。
そして日本一から招待されるための行動を
須江監督は率先して実践されています。
今回の対沖縄尚学敗戦後のインタビューでも、
相手チームを称賛する言葉と
自チームの選手たちの頑張りを全力で称える
プラスの言葉で溢れていました。
中継を見ていた側として今試合の敗因は
「あれがなければ…」という
守備のミスによるところが大きかったと思います。
しかし、そんなことは百も承知の監督には、
甲子園で戦うというのはミスも含めて実力。
つまり、日本一から招待されるに値しなかった、
(=相手の方がそれに値するに相応しかった)
と素直に胸に納める潔さがあります。
それだけ、やれることはやり切って戦うのが
「密な青春を野球にささげた」全国の一流球児が集う
甲子園という場なのでしょう。
それにしても、日本一激しいチーム内競争をして、
日本一に招かれる行いを日々実践し、
それでもほとんどの選手は甲子園の土を踏むことができない
という環境がありながら戦い抜いた結果の責任は
全て監督がとるという姿勢は人の心を動かします。
2022年の優勝パレードでは、
「私ではなく選手がすごいのです、
周囲への感謝を真っ先に述べる謙虚さが注目されています。
ベンチ外となった3年生には、
「君が打撃投手として投げてくれたから、エースが育った。
君の球は間違いなくこのチームを強くした」と語り、
その選手は「自分の役割を誇りに思えた」
ここぞ!というときに
相手が欲しいもの(=気持ちよく次の行動に移れる言葉や態度)
を提供できるリーダーは組織の結束力を強くします。
信頼関係が構築され、内部からファンを生み出す力が
そういうリーダーにはあります。
内部から生まれるファンはその愛を外部に向けて発信するので、
結果的に外部にファンが増え、応援されるチーム(組織)
ちなみに須江監督は目標を数値化、言語化し、伝えることで、
相手の納得を引き出すことにも長けています。
この納得感というのが何よりも今の時代にフィットしていて、
選手のモチベーション維持の源になっているように思います。
今年も仙台育英というチームの戦いぶり、
そして、それでもなお応援される”負けっぷり”を見て
応援されるチームの真の強さを垣間見ることができました。
さて、現在の就学前教育保育業界の動向は、
入園の低年齢化が激化し、それに伴い職員確保の激化で
慢性的な”人不足”が経営の”足枷”となっています。
低年齢からの受け入れが実現できなければ、
入園児の減少は避けられない状況にありますが、
新制度では収入が傾斜配分設計になっているため、
子ども数の減少による収入への打撃は比較的緩やかです。
ただ、今後も人不足は加速していきますので、
自園への流入減少の流れ(減少している園は)は
どこかで歯止めをかけなければなりません。
打開策に特効薬はありませんが、
内部の信頼関係を構築していくことが重要な局面です。
採用・育成においては、
なぜ自分はこの園を選んだのか?
将来どこへ向かって進んでいくのか?
どのくらい稼ぐことができるのか?
キャリア形成の道筋はたっているのか?
この辺りの整理をしておくことが重要ですし、
募集においては、
利便性の整備(保育(機能)の包み込み)は基本としつつ、
やはり、園の独自性である、
どんな子どもを育てたいのか、
もっと言えば、どんな未来をつくりたいのか?
それは、子どもにとって、地域にとって
多くの共感が生まれるものなのか?
この辺りを整理して丁寧に伝えていく必要があります。
ここになら我が子を預けて安心だ!
この園とともにこどもの未来を育みたい!
この園で働きたい!
こんな環境で自分のキャリアを磨きたい!
そんなモチベーションが湧く環境が
今の時代の募集・採用マーケティングを活性化させます。
遠回りに見えますが、一番の近道になります。
ぜひ、